夢をよく見る人にはどんな特徴があるの?
夢を見ないまま朝を迎える人もいれば、毎晩のように夢を覚えている人もいます。 「夢を見ない人の方が深く眠れている」というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
では、なぜ人によって夢を見る頻度が違うのでしょうか?そして、夢をよく見る人にはどんな特徴があるのでしょうか。
「夢をよく見る人」は、実は「夢をよく覚えている人」
昨日、どんな夢を見たか覚えていますか?中には「毎晩のように夢を見る」という方もいますが、実は“夢を見る回数”そのものに大きな差はありません。違うのは、夢を覚えているかどうかなんです。眠りが浅い人や、夜中に何度も目が覚める人ほど夢を覚えている傾向があります。 小さな音でも目が覚めてしまうような敏感な方は、夢を記憶しやすいタイプといえるでしょう。
つまり、誰でも同じように夢を見ていますが、浅い眠りが長かったり途中で目を覚ましたりすると、その夢を覚えていられるのです。 もし「毎日のように夢を見る」と感じるなら、睡眠の質が低下しているサインかもしれません。睡眠時無呼吸症候群など、何らかの睡眠トラブルが隠れている場合もあります。
なぜ私たちは夢を見るの?
睡眠の段階と夢の関係
私たちの睡眠は、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という2つの段階に分かれています。 このうち、夢を見ているのは「レム睡眠」と呼ばれる浅い眠りのときです。レム睡眠の間、体は休んでいても脳は活発に動いています。 このとき脳は、日中の出来事や感情、記憶を整理しながら、それらを組み合わせて夢をつくり出していると考えられています。
つまり、夢は私たちの心と脳が一日の経験を消化し、整理するための自然なプロセスなのです。

また、レム睡眠のあとに深いノンレム睡眠へと移行し、そのまま目覚めた場合は、夢を見たこと自体を忘れてしまうことがあります。ある研究では、「夢を見ない」と答えた人をレム睡眠中に起こしてみたところ、多くの人が「夢を見ていた」と答えたという結果も報告されています。つまり、誰もが眠っている間に夢を見ています。 ただし、レム睡眠中に目が覚めたり、浅い眠りの時間が長かったりすると、夢を記憶として残しやすくなるのです。
夢を頻繁に見るときに考えられる原因
一般的に、7時間眠る場合のレム睡眠は合計でおよそ1時間半ほどといわれています。もし「最近やたら夢を見る」と感じているなら、レム睡眠の時間が増えている、またはそのサイクルが頻繁に繰り返されている可能性があります。ストレスやうつ状態など、精神的な負担があると、脳や自律神経が夜間でも活発に働きやすくなり、眠りが浅くなることで夢を覚えやすくなります。また、寝る2〜3時間前にスマートフォンやテレビなど刺激の強いコンテンツを見たり、カフェインやアルコールを摂取したり、激しい運動を行うと、睡眠の質が低下し、夢を見る回数が増えることもあります。
さらに、睡眠時無呼吸症候群のように、睡眠中に呼吸が止まる症状がある場合や、夢の中の行動を実際にしてしまうレム睡眠行動障害の人も、夢を鮮明に覚えている傾向があります。これらはいずれも、レム睡眠中に覚醒が起こることで夢の記憶が残りやすくなるためです。

夢を見ない夜と深い眠りの関係
「昨日は夢を見なかったから、よく眠れた」と感じたことはありませんか?実際には、誰でも眠っている間に夢を見ています。ただし、その内容を覚えていないだけなのです。夢の印象がぼんやりしていたり、起きてすぐに忘れてしまった場合、「夢を見なかった」と感じやすくなります。科学的には、レム睡眠の最中に夢が長期記憶として定着しなかったり、深い眠り(ノンレム睡眠)の時間が長くレム睡眠が短かった場合、夢の記憶が残らないと考えられています。
つまり、「夢を見なかった=よく眠れた」というのはあながち間違いではなく、深い眠りがしっかり取れていたサインともいえるのです。
悪夢を見る理由
なぜ私たちは悪夢を見るのでしょうか?悪夢は、強いストレスや睡眠障害などが原因で起こることがあります。夢をよく見る人と同じく、睡眠の質が低下すると悪夢を見やすくなる傾向があります。私たちの体はストレスや体調の変化にとても敏感です。
夢は日中に感じた感情や出来事を整理する働きを持つため、心が不安定なときや緊張が続いていると、その内容が悪夢として表れることがあります。悪夢を減らすためには、就寝前にストレッチや瞑想を取り入れて心を落ち着かせることが効果的です。
また、寝る直前までスマートフォンを見ない、カフェインを控えるなど、眠る前の環境を整えることも大切です。
健康状態によって変わる悪夢の種類
悪夢の内容には、私たちの心身の健康状態が深く関わっています、 脳が疲れていたり、機能が低下していると(たとえば認知症やパーキンソン病など)、攻撃されたり追いかけられたりするような不安や恐怖を伴う夢を見やすくなる傾向があります。
また、同じような不快な夢を何度も繰り返し見る場合は、何らかの睡眠障害が隠れている可能性もあります。 睡眠中に血圧が上昇したり、不整脈が起こったりすると、脳や神経が刺激を受け、悪夢が頻発することもあります。このように、悪夢は心だけでなく、体からのサインである場合もあるのです。

「金縛りにあった」と感じる夢を見るのは、睡眠中に体と脳の状態がずれてしまうためです。本来、レム睡眠中は夢を見ている間に体が動かないよう、筋肉を弛緩させるホルモンが分泌されています。しかし、その働きがうまく調整されないと、脳だけが覚醒し、体が動かないまま意識が戻る――いわゆる“金縛り”のような感覚が生まれます。
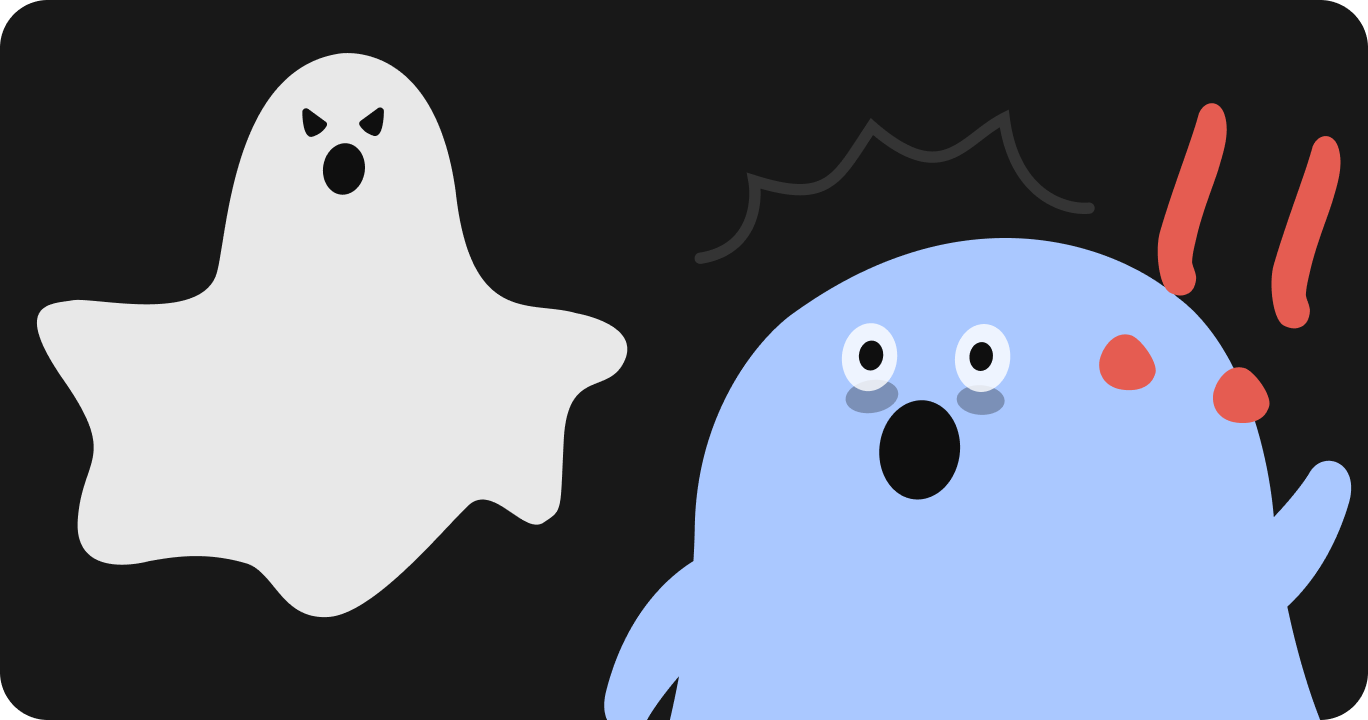
また、重い枕や布団で体が圧迫されていたり、横向きで腕を下敷きにしていたりするなど、身体的な要因によっても同じような夢を見ることがあります。こうした状態が続く場合は、睡眠の質が乱れているサインかもしれません。寝具の見直しや睡眠姿勢の調整を行い、体に負担をかけない眠りを心がけましょう。
夢を見ずに、ぐっすり眠りたいあなたへ
朝起きたときに夢を覚えていないようにするには、「睡眠の質」を高めることが大切です。
深い眠り(ノンレム睡眠)の時間を長く保ち、浅い眠り(レム睡眠)を短くすることで、よりすっきりとした目覚めにつながります。
- 睡眠リズムを一定に保つ:毎日ほぼ同じ時間に寝て、同じ時間に起きる習慣をつけましょう。
- 就寝前の刺激を減らす:寝る2〜3時間前はカフェインやアルコールを避け、激しい運動やスマートフォンの使用も控えることがおすすめです。
- ナイトリーを使って、睡眠の質を整える:ナイトリーは、モノラルビートによって深い睡眠へと導くサポートを行います。
ナイトリーは、モノラルビートを通して、あなたの眠りをより深く、質の高いものへと導きます。
心地よい眠りと爽やかな目覚めのために、ナイトリーはこれからもあなたのそばで寄り添い続けます。
