忙しい日々の中で、**「もっと多くのことをこなすために、睡眠を削らなければならない」と感じることはありませんか? 学生は遅くまで勉強し、社会人は締め切りに追われて徹夜し、早起きをして時間を有効活用しようとする人もいます。 夜遅くまで作業をしたり、朝早くから活動することで、「より集中できている」「頑張っている」**と感じることもあるでしょう。
しかし、一晩や二晩の睡眠不足は耐えられたとしても、それが続くと確実にパフォーマンスは低下していきます。 せっかく睡眠を削って時間を作ったのに、なぜ生産性は落ちてしまうのでしょうか?
時間を増やしても、効率は下がる
睡眠不足が続き、睡眠負債が蓄積すると、脳は疲労しやすくなり、集中力が低下します。 研究によると、1日10時間以上働く人や、一晩の睡眠が6時間未満の人は、注意力・反応速度・認知能力・問題解決能力が低下し、その影響は飲酒時と同じレベルであることが分かっています1 2 3。
実際、1晩に7時間未満の睡眠が続くと、血中アルコール濃度(BAC)が0.05%以上のときと同等の認知機能低下が起こるとされています。 多くの国では、BACが0.05%を超えると飲酒運転で免許停止の対象になる4ほど、脳の働きが鈍くなるのです。
結果として、長時間勉強しているのに、なかなか内容が頭に入らない、仕事でのミスが増え、効率が悪くなるといったことが起こります。 結局、睡眠を削るほど「長く働くのに成果が出ない」状態に陥ってしまうのです。
記憶力の低下
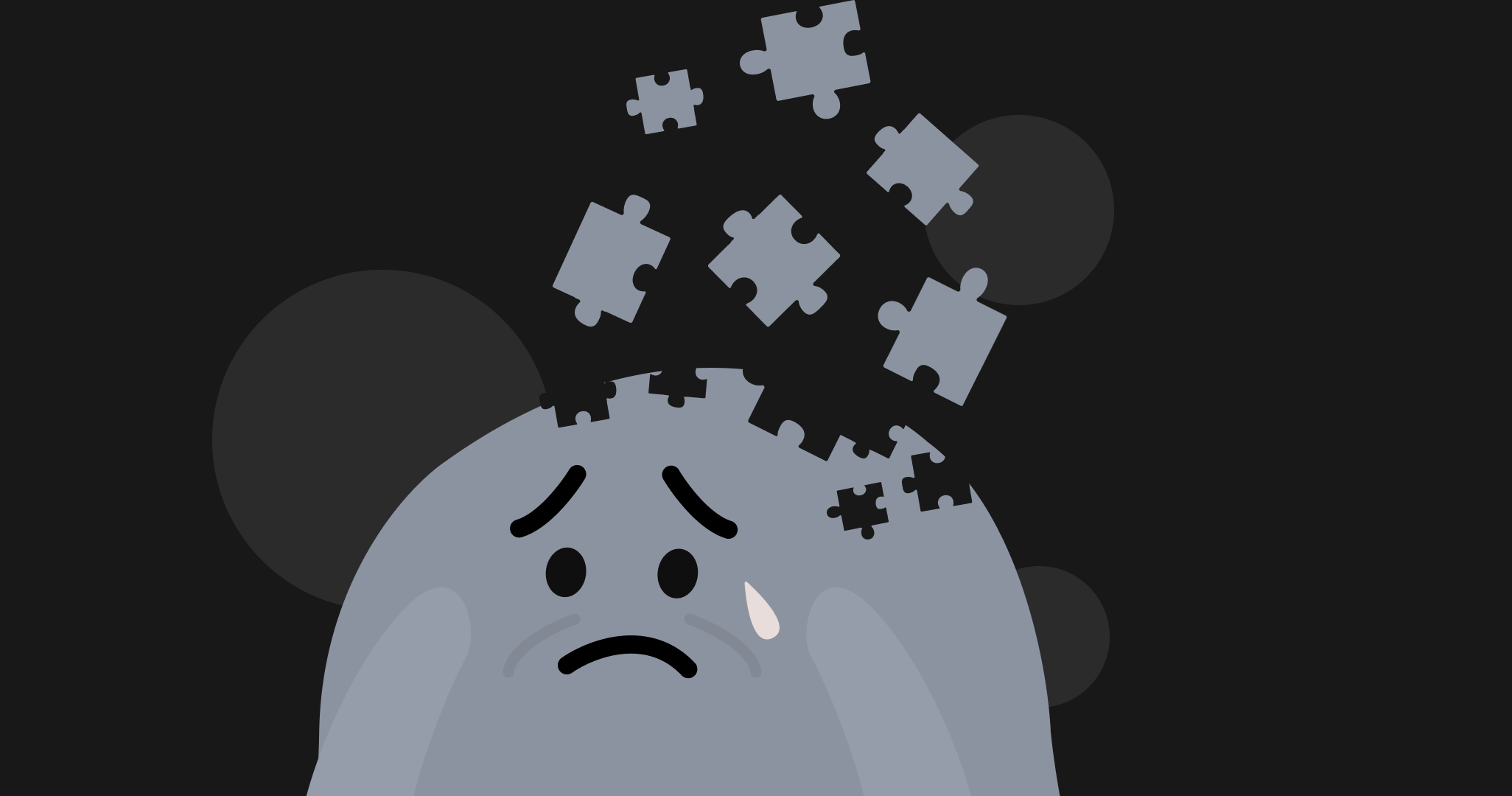
私たちの脳は、睡眠中に新しい情報を整理し、長期記憶として保存します。 特に深い睡眠(ノンレム睡眠)やREM睡眠は、学習と記憶の形成に不可欠です。
しかし、睡眠不足になると、こうした重要な睡眠段階が十分に確保できなくなり、新しい知識を定着させにくくなる、過去に覚えた情報を思い出す力も低下するといった影響が現れます。
さらに、記憶を引き出すスピードも遅くなり、「思い出せそうで思い出せない」状態が頻繁に起こるようになります。
イライラしやすくなり、感情のコントロールが難しくなる

睡眠不足は、私たちの感情のコントロール能力にも影響を及ぼします。
感情を司る脳の**扁桃体(へんとうたい)**が、ネガティブな刺激に過剰に反応するようになる5ため、ストレスを感じやすくなります。 また、他人の感情を正しく読み取る力が低下6し、誤解や対人関係のトラブルを引き起こしやすくなります。
結果として、ちょっとしたことでイライラしやすくなる、ストレスをより強く感じるようになる、精神的にも消耗しやすくなるという負のスパイラルに陥ってしまうのです。
「睡眠をとる=怠ける」ではない。むしろ賢い戦略!
「夜遅くまで勉強する」「徹夜で仕事をする」「朝早く起きる」=生産性が上がるというのは、実は大きな誤解です。
現実には、長時間働いても、作業効率が悪化する、記憶の定着が悪くなり、学習効果が低下する、ストレスが増え、精神的に不安定になりやすいといった悪循環が生まれ、かえってパフォーマンスが低下してしまいます。
睡眠を優先することは、怠けではなく、むしろ「賢く働くための戦略」です。
より充実した明日を迎えるために、今夜からナイトリーと一緒に良い睡眠をとりませんか?
